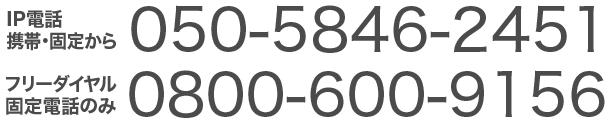お客様の声[AEDレンタル]
2008年08月6日
こんにちわ 救命コムの門田です
救命コムのレンタルサービスをご利用いただいた、お客様の声を!
これから、このブログで少しずつご紹介させていただきます
お客様の声
場所:岡山県
ユーザー:小学校PTA関係者
商品:AEDレンタル[ハートスタートHS1レンタル]
レンタル期間:5日間
==========================================
『安心を頂きました。
使わなくてよかったと心から思っています。』
==========================================
少ないコメントですが、なにより心のこもった言葉だと思います。
深い言葉ですね
救命コムは、AEDレンタルを通して安心を全国にお届けしていることを肝に銘じ、安心してレンタルいただけるよう、今後も努力してまいります。
安心を受け取っていただき、とても嬉しく感謝しております。
子供達を思う、ご両親の心、『使わなくて良かった』
の一言に尽きますね
水辺の事故に注意!
2008年08月4日
暑い
夏ですね~情熱の夏に突入しております
この季節は、子供達は夏休みでもあり活発に活動されますね。
救命コムのレンタルサービスをご利用いただきありがとうございます
全国のさまざまな場所でAEDをレンタルしていただき、備えていただいておりますが、今年の夏もAEDの使用事例が増えてきました
ご注意ください
熱中症・水辺での事故など
最近、立て続けに救命事例が発生しておりますのでご注意ください
★ 【救命コムでは、事後のサービスもしております】
救命時の心電図データを無償提供
事後の治療に役立てていただいております。
音声データは専用ソフトが必要なため、対応できないこともございます
心臓が原因での、心肺停止や体調不良などの場合、病院に運ばれてからでは、治療がなかなか進まないケースがあります。
そんな場合には、心電図データが役立ちます
倒れた時に、なにが原因で心肺停止や体調不良になったのか原因が判ると、すみやかな治療にはいることができます。
これは、意外と大きなことです
みなさん知っておいてくださいね
また、救助者やイベント責任者を交えての反省会なども対応いたします
何事も、反省が必要ですね!
その際は、ご相談ください
この夏、やっぱり心配だからAEDをレンタルして備えたい方!
水辺の備えや、屋外の備えに安心の耐水性の高さ!
耐衝撃性に強く、液晶モニタ搭載という優れもの!
ハートスタートFR2をお勧めいたします
皆様の、安心と安全に貢献し
一人でも多くの命が助かりますように祈ります